山科毘沙門堂吟行記
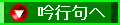
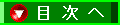
平成17年11月13日 野田ゆたか
11月13日京都市山科区内の毘沙門堂及び聖天堂一帯で行われた吟行に参加した。
山科区は、京都市の東端に位置し、平安時代から京都の東の玄関口、交通の要所として栄えた町であり、西は東山連峰、北は大文字山、如意ケ獄、東は音羽山、牛尾山と三方を山に
囲まれている。南は、伏見区の醍醐地域と接し区内には、平安時代のロマンを感じさせる史跡の数々が残っている。
吟行は、貫野浩先生のご案内でJR山科駅前を午前10時に出発した。目的地の毘沙門堂までは1キロメートル強、探訪しつつ歩いて30分の距離にある。
駅前を出て直ぐ明治23年に完成したという発電、灌漑、舟運などで京都の近代化に寄与した琵琶湖第一疏水の橋に至る。
疏水は、水量豊で流れが速く、両岸は「紅葉且つ散る」の景であった。
ここでは
落葉乗せ疏水の流れ早かりき 澄子
疎水路に沿ひて紅葉の濃かりけり ゆたか
などの句が詠まれた。
第一疏水からは、なだらかな毘沙門坂を上り、途中、赤穂浅野家の縁の瑞光院にお参りをする。瑞光院の墓所中央には、大石良雄が建てた浅野長矩の供養塔と討入り後、切腹した義士四十六名の遺髪塔がある。
毘沙門坂では、「紅葉、落葉、実南天、七竈の実、団栗類の木の実、石蕗の花」など「晩秋と初冬」の景が広がっていた。また天候も、「秋日和とも冬日和とも」取れる状態であった。
この毘沙門通りでは
毘沙門の道と伝へて紅葉濃し 佐知
ゆるやかな坂の毘沙門道小春 律子
山装ふあまたの錦重ね着て ゆたか
などの句が詠まれた。
毘沙門堂は、紅葉の名所として知られ、毘沙門天を本尊とする天台宗の門跡寺院、寺の起りは古く奈良時代に遡る。
急な石段を登って仁王門をくぐると、紅葉に彩られて本殿、宸殿、霊殿などが並んでいる。宸殿は、後西天皇の旧殿を賜ったものです。
内部の障壁画、襖絵は狩野探幽の養子益信の作、見る人の動きによってこれほど大きく動いて見える絵は、他に類を見ない。
この堂の周辺では
山裾の迫りて紅葉濃きみ寺 佐知
掃くもよし掃かぬもよし寺紅葉 良一
桜木の紅葉枝垂れし勅使門 ゆたか
本殿、宸殿では
玉座の間紅葉明りに開け放ち 佐知
応挙絵の動く鯉の目小六月 舟津
夢一字屏風を坊の玄関に 美和子
などの句が詠まれた。
毘沙門堂の西北に接して双林寺、通称聖天堂がある。
双林寺は、毘沙門堂門跡の山内塔頭として、寛文5年(1665)に公海大僧正により建立されたもので、山門を入って東側にある堂には、男女2体の和合の状態を示す聖天像が祀られていると聞くが、一般には公開されていない。
また山門の正面には、不動明王像、準提観音像、弁財天女像などが祀られ、西側奥には不動の滝がしつらえられ、小さな不動明王の石像を祀った行場となっている。
双林寺では
宝珠乗せ聖天の屋根冬日濃し 美和子
山裾を昏めて冬の行の滝 窓城
境内のみくじ結ばる実南天 徹
山を背に紅葉がくれに弁天堂 律子
などの句が詠まれた。
さらには、この吟行の道中を通じて
ちんどん屋会ふも山科街小春 窓城
猿の出る貼紙ありて紅葉晴 宮子
などの句が詠まれた。
吟行を終え、午前11時50分毘沙門堂門前に集合し出発地に戻り、昼食を済ませた後、午後2時から駅前の生涯学習センターの研修室において句会をもった。
句会後は、選者の西﨑佐知先生から句評、問題句の指導などがあり充実した吟行句会であった。
吟行中の私は、霊場を弘法大師と巡拝する遍路よろしく、俳聖松尾芭蕉と「同行二人」の心境で臨んだが、俳聖に見放される場面もあり、俳聖お見通しの日頃の不品行、不勉強を反省した次第です。
ご参加者の皆様ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
山科毘沙門堂が紹介されているホームページ